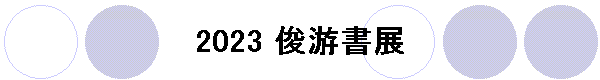
�i�����䂤����Ă�j
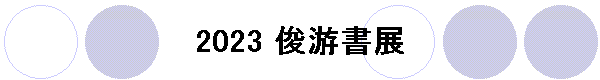
�i�����䂤����Ă�j
���Ȃ����l�߂�
���q�l�ł��B
�P�P���Q�X���i���j�`�P�Q���P���i���j |
2023�@�r�����W
2023�N�i�ߘa�T�N�j
�P�Q���T���i�j�`�P�O���i���j
���Óc�E�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[�ɂ�
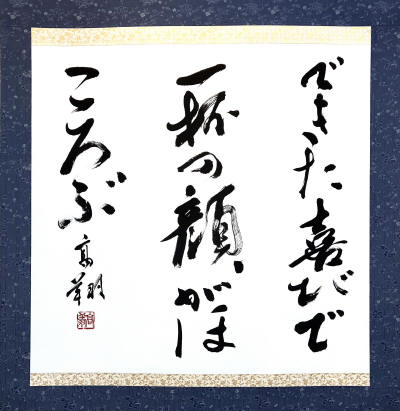 |
�@ | 
|
|
�������� |
�@ |
���{�퐶 |

|
�@
2022�@�r�����W
2022�N�i�ߘa�S�N�j�P�Q���U���i�j�`�P�P���i���j
�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[�ɂ�
�@
|
�������� |
�@ |
���{�퐶 |
|
���r���a |
�@ |
�������� |
|
���䐽�M |
�@ |
�ԉH�щp |
|
��ˍK�q |
�@ |
���c�L�� |
�@
|
�@
�ȉ��́A�ߋ��ɊJ�Â̏��W�ł��B
��U�� �r����W
�����Q�U�N�P�P���Q�U���i���j�`�P�Q���P���i���j
�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[
��������̂�����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@
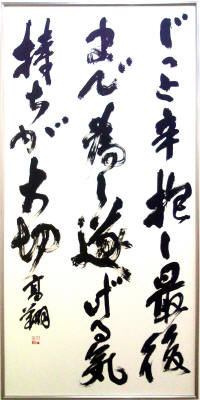 �@�@
�@�@
��������
�@
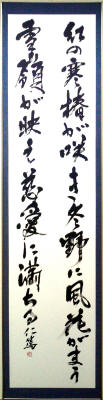 �@�@ �@�@ �@�@�ޗǐm�� �@�@�ޗǐm���@ |
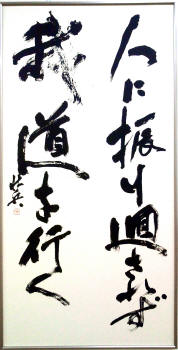 �@�@ �@�@ �@�@���c�s�� �@�@���c�s���@ |
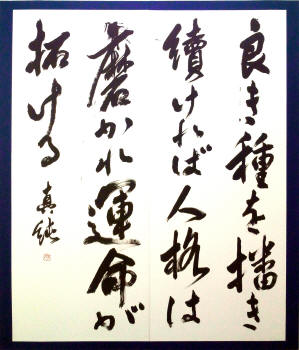 �@�@ �@�@ ��c�^�� �@ |
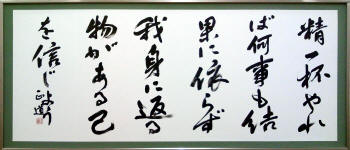
|
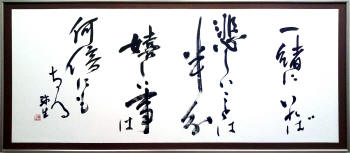
|
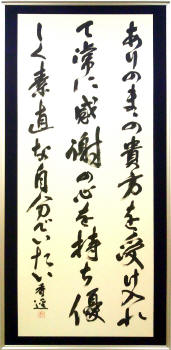 �@�@ �@�@ �@�@���؍�� �@�@���؍�� |
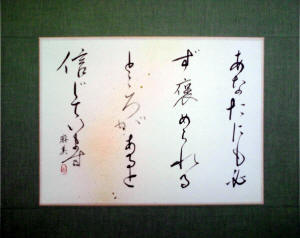 �@ �@ �ΐ얃�� |
���r�݂̂� |
�ȉ��́A�w���̊F����̍�i�ł��B�i�A���t�@�x�b�g���j
�摜���N���b�N����ƁA�g��\�����Ă����ɂȂ�܂��B
�@
|
�@���A���܂ŁA����ȏ��W�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�W����Ɍ������č�i�Â���ɂނ��Ⴍ����ɂȂ��Ď��g�݁A���̐��ʂ����Ŏ����̊�Ŋm���߂邱�Ƃ��A��B�̈�Ԃ̋ߓ����Ǝv���Ă��܂��B�F�l�ɂƂ�܂��āA�ǂ̂悤�ȏ��W�������ł��傤���B |
�@
���@�@�@���@�@�@��
�ȉ��́A��T�W�̗l�q�ł��B
��T�� �r����W
����25�N�P�P���P�S��(��)�`�P�X��(��)�@�P�O�`�U���i�ŏI���͂T���܂Łj
���ؒ��E�S�[���f���M�������[�i�҂��V�e�B�[�R�K�j �ɂ�
�@�@�@JR�E���l�s�c�n���S�A���ؒ��w���n�����u��т����݂��v����
�@�@�@�݂ȂƂ݂炢���A�n�ԓ��w�P���o���k���R��
�@
|
�������� �@ |
|
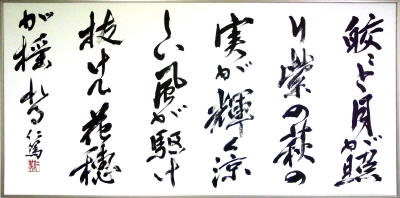 �ޗǐm�� |
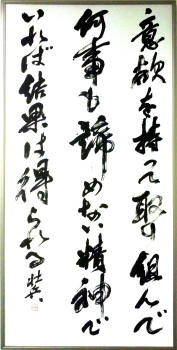 �@�@�@�@���c�s�� �@�@�@�@���c�s���@ |
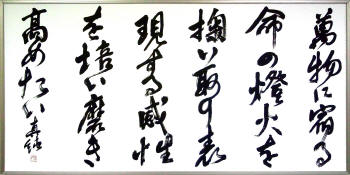 ��c�^�� �@ |
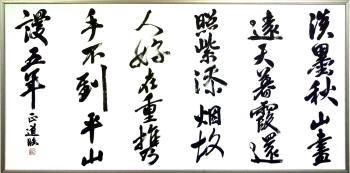 �������� �@ |
���@�@�@���@�@�@��
�ȉ��́A��S�W�̗l�q�ł��B
����24�N�P�Q���U��(��)�`�P�P��(��)
�@
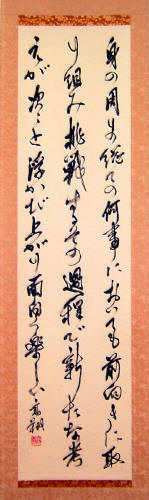 �@����܂ł����ݖ�ɂĊJ�Â��Ă܂���܂������ď��������̏��W���A���ؒ��ɂāA�u�r����W�v�Ɩ��O�������ĐV���ɃX�^�[�g���邱�Ƃɂ��܂����B�u�r�����悫�F�v�̈Ӗ��ł��B�����������A��܂������������͋C�̏��W�ɂ������Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B �@����܂ł����ݖ�ɂĊJ�Â��Ă܂���܂������ď��������̏��W���A���ؒ��ɂāA�u�r����W�v�Ɩ��O�������ĐV���ɃX�^�[�g���邱�Ƃɂ��܂����B�u�r�����悫�F�v�̈Ӗ��ł��B�����������A��܂������������͋C�̏��W�ɂ������Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B�@���́A�o�i�\��̍������č�u�g�̎���̑��Ẳ����ɂ����Ă��@�O�����Ɏ��g�ݒ��킷��@���̉ߒ��ŐV���ȍl�������X�ƕ����яオ��@�ʔ����y�����v�ł��B����̐��������������ł��肽���Ƃ����肢�����߂܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@���@�@�@�� �@�P�P���R���A���Z���ȉ��̊F����̍�i���A�\�����֎����Ă������������܂����B�����ł̐���ɂ͂P�J���������A�ŏI�I�Ɉ�Ԃ�����i�P�_���o�i���܂��B�S�����킹��ƁA��i�̎R�ɂȂ�܂��B�F���ꐶ������������i�ł�����A���낻���ɂł��܂���B�������ɂȂ��āA��i��I�т܂����B�i���A���̎ʐ^�j  �@ �@
�@��ꕗ�i�ł��B  �@ �@
 �@ �@  �P�Q���W���A�u���[�Y�x�C�z�e���ł̏j���i�ł��B �P�Q���W���A�u���[�Y�x�C�z�e���ł̏j���i�ł��B |
�@