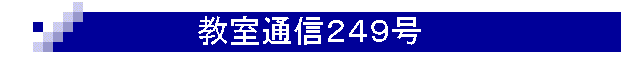
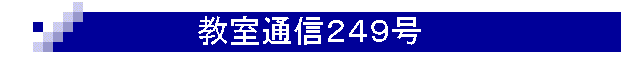
2025年(令和7年)5月18日増補
高翔書道教室 046−272−4001
ホームページ http://home.g03.itscom.net/kohshoh
昇段級試験 成績発表!
|
学生部の皆様、進学・進級おめでとうございます。書道教室でも新学期の話題が溢れていて、希望に満ちた季節という感じです。俊游誌4月号は、3月にしめきりました春の昇段級試験の成績発表号です。段・級は上がっていましたか?どうぞご覧ください。 1.5・6月の授業日について ( )はお休みです。 |
|
|
5月 |
中央林間 |
中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | しらとり台 |
| 日 | 月 4〜7時 |
火大人 4〜8時 |
水子供 2〜7時 |
木 2〜7時 |
金 2〜8時 |
土 2〜7時 |
| 4月28 | (29) | (30) | (1) | (2) | (3) | |
| 4 | (5) | (6) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | (29) | (30) | (31) |
| 6月 | 中央林間 奈良先生 |
中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | しらとり台 |
|
日 |
月 |
火大人 |
水子供 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
![]()
|
![]()
|
![]()
作品のことばを選ぶ(4月28日増補) |
![]()
幼児・小学校1・2年生の皆様へ(5月18日増補) |