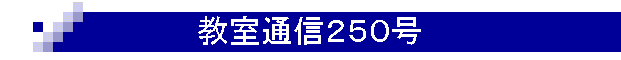
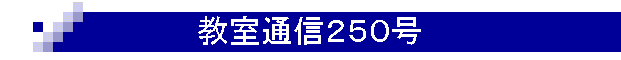
2025年(令和7年)7月29日増補
高翔書道教室 046−272−4001
ホームページ http://home.g03.itscom.net/kohshoh
夏休みの書道教室
梅雨とはいえ、暑い日が続いていますね。どうぞ皆様、ご自愛ください。一年の廻りはうまくできていて、これからエネルギーをため、学校の夏休み、秋の昇段級試験そして俊游書展へと繋がっていきます。これから大いに張り切って取り組みましょう |
|
|
7月 |
中央林間 |
中央林間 |
中央林間 |
中央林間 |
中央林間 |
しらとり台 |
|
日 |
月 |
火大人 |
水子供 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | (29) | (30) | (31) |
|
8月 |
中央林間 |
中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | 中央林間 | しらとり台 |
| 日 | 月 4〜7時 |
火大人 4〜8時 |
水子供 2〜7時 |
木 2〜7時 |
金 2〜8時 |
土 2〜7時 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6宿 | 7宿 | 8宿 | 9宿 |
| 10 | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | (29) | (30) |
![]()
|
![]()
|
![]()
書に卒業はない |